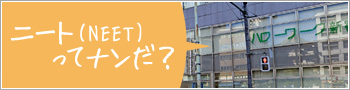ブラックフラグ立ちまくり! 働いたら負けかなと思ってる…
「ブラックフラグ」 とは、就職活動 (就活) や転職活動を行っている求職希望者が、「この会社はヤバそうだ」「どう考えてもブラック企業だ」 と感じるポイントや、「求人情報や面接の時にこういうことが見えてくる会社はブラック」 だとする目印、キーポイントのことです。
そうしたポイントがある場合は 「ブラックフラグが立ってる」、途中で見えてしまった場合は 「ブラックフラグが立った」 となります。 なお就職してしまった、実際にブラック企業だった場合には、「ブラックフラグ消化」「フラグ回収」 などとなります。
ちなみに フラグ (Flag) とは日本語に訳すと 「旗」 という意味ですが、「フラッグ」 と呼ばず 「フラグ」 と呼ぶ場合には、ゲーム などでその先のストーリー展開やゲーム内の状況が大きく変わる節目や分岐点になる 「目印」 のようなものを示します。 似たような経緯で広がった言葉のうち有名なものには、この他 死亡フラグ などもあります。
ブラック企業…それは働く人をすり減らしすり潰す伏魔殿
一般的なブラック企業の定義としては、給料が安い、休みが少ない (もしくはない)、結果的に離職者が多く安定しないなどの、従業員に劣悪で過酷な就労 環境 を強いる会社のことになります。 パソコン通信 時代に大学の学生用の 掲示板 や、そこでの情報の集積地である大手商用ネットなどでの新卒採用就職のための情報交換、コミュニティなどで言葉として生まれ、後に インターネット の時代となって定着しました。 元ネタ は ネットスラング でしょうが、現在は普通の若者言葉、就活スラングと云って良いでしょう。
パソコン通信の時代、とりわけ後半 (1990年代後半) は、いわゆるバブルの崩壊もあって就職氷河期に突入。 就活のための情報交換の場も 雰囲気 が一変しましたが (バブルの頃は、「上手な内定の断り方」 なんて コメント が多かったものでした)、求人に応募した人が 「あの会社はヤバそうだ」 とか、過去に働いていた人が内部告発のような形で会社のヤバさを 書き込み したりして、概念 と言葉が一気に普及。
リクルート社の求人雑誌や各企業の発信する 「表向きの求人情報」 とは別に、実態に即した草の根の求人情報が大きく発展しましたが、「募集広告にこういう文言のある会社は要注意」 なんてのが、様々取り上げられました。 とりわけインターネット掲示板が大きく発展する 1990年代末期は、正社員の有効求人倍率が 0.39 などの時代でしたので、「ネタ で遊べる状況じゃない」 利用者が、切実感、切迫感のある言葉として 「ブラック企業」 という単語を使っていました。
なお対義語は 「ホワイト企業」、その中間、もしくは情報が少なく判別ができない企業を 「グレー企業」 と呼びます。 またしばしば 香ばしい なんて表現をする場合もあります。
「若い人が多い会社です!」…「みんなすぐに辞めるからじゃないの?」
|
激務・強制残業 過度の転勤 不規則勤務 高ノルマ 薄給・歩合給・低待遇 ワンマン経営 犯罪・違法行為の奨励 社風が異常 コネ採用・天下りの蔓延 差別待遇・嫌がらせ・社内 いじめ |
| ブラック企業にありがちな特徴一覧 |
主な 「ブラックフラグ」 と云えば、例えば 「社員の平均年齢が低い会社」 を、表向きの求人広告では 「若い人がたくさんいて、また活躍もできる、明るい会社です」 などと表現しますが、実際は 「就職した人があまりの会社の酷さにみんな辞めてしまうから、結果的に若いだけ」 だったりします。
あるいは 「土日完全週休2日制」 が、実際は 「逆に土日以外の祭日や盆暮れの休みがないか、まともに取れない」 だったり、「ノルマはありません」 が、実際は 「会社からノルマは課せられないが、それよりずっと大きな自主目標を立てさせられ、達成できないと大きく給料が減らされる、あるいはクビになる」「未経験者歓迎」 と云っておきながら、本当に未経験で応募したら即座に断られる…なんてのがあります。
この他、各種社会保険がないとか、正社員なのに給与待遇が時給や日給計算だったり、面接時に入社後の給与体系を、恐ろしく低額の固定給か恐ろしく高額の歩合給かのどちらにするか選ばせたり、この就職不況の中で面接もせず書類だけで採用 (全員採用して試用期間と称してタダ働き同然にこき使われてすぐに解雇) とか、やたら出たがりの社長がどう考えてもカタギじゃない、アレオレ の自慢が酷いとか、社長・専務・常務ほか役職が全員親族で固められているとか、社内研修も何もないとか、「こういう会社で働いたらやばいぞ」 という情報が様々集積されるようになりました。
またそうした体質の会社が多い特定業種 (派遣やパチンコ、消費者金融、英会話 学校、各種教材、訪問販売を中心とする営業、配送業、介護や一部の末端医療、飲食、弱小ゲームソフトハウス、アニメ下請け、下流SEなど) を、その時点でそのまま 「ブラックフラグ」 とする場合もあります。
さらに些細な兆候としては、社長室だけがやたらと豪華、逆に極端に社長の生活が質素、「人材」 を 「人財」 とか 「人在」 とか自己満足気味な妙な誤変換であらわす、人事担当者や営業が 茶髪 だ、トイレに独りよがりな勢いだけの変な社訓がことさらに貼ってある、問い合わせの電話を掛けたら相手がやたらテンション高いとか、素手で便所を 掃除 などの新人研修、キャッチフレーズ が 「こんな会社みたことない」「どこにもない」 などなど、端々に 「伏線」「フラグ」 が 「ここは 地雷 ですよ…踏んだらえらいことになりますよ…」 なんて見え隠れしていたりもします。
とくに社長がやたらと 「夢を持て」「思えば夢は叶う」「諦めず努力し続ければかならず道は開ける」 などと力説するのも要注意でしょう。 これは要するに、「夢のために今は我慢しろ」 と云っているのと同じです。 「若い時の苦労は買ってでもしろ」 とはいいますが、それを若者に向かって説くのは、新人社員や若者をこき使う立場の、管理職や老人であるのを忘れてはいけません。
一般的なブラック企業にプラスして、おたくが嫌がるブラック要素
これら一般の 「ブラックフラグ」 のほか、おたく系 の人たちがとりわけ嫌がるのは、自分の自由な時間 (「おたく」 としての 趣味 に費やす時間) を食いつぶす長時間労働やいつ終わるとも知れない残業、肉体労働だったり過大なノルマがあるなどのきつい仕事、あるいは飲み会やリクリエーションと称した 馴れ合い (アットホームな職場は、逆に馴染めないと 地獄 です)、会社の体質が体育会系 (というより DQN 体質) だったり閉鎖的だったり、社長や幹部が最悪 (とりわけ前述した一族経営などが嫌われますね) な会社がそう呼ばれるようです。
求人就職環境は、バブル崩壊後のいわゆる 「失われた 10年」 を経てかなり改善していますが、都市部以外では依然として厳しい状況に変わりはなく、また非正規雇用が増えたり、「働くのがイヤ」 と称される ニート がクローズアップされるようにもなり、「ブラックフラグ」 は切実な情報として、あるいはネタとして、まだまだ ネット を賑わせているようです。
その後一時的に景気が多少持ち直したこともあり、「そもそもブラック企業に文句をいう前に、ブラック企業に行こうとしている、あるいはブラック企業しか行けないような自分を何とかするべき」 なんて意見も出てきていますが、まあ引っかからないように注意するのは悪いことじゃありませんね。
2008年になり、100年に一度の世界的不況、世界同時株安の余波が日本にも及び、さらに2009年の政権交代による民主党のむちゃくちゃな経済政策や温暖化対策などにより、俗に鳩山不況などと呼ばれる状況も起こっていますが、前後して急激に 「ブラック企業」 や 「ブラックフラグ」 という言葉に、リアリティ が再び宿るようになっています。 2011年には、日本がルール作りに参加できない形での TPP (環太平洋戦略的経済連携協定) への将来の参加も実質的に表明され、今後は熾烈な国際競争に国内産業までが晒されることにもなるかも知れません。
ブラックが当たり前の時代には、なって欲しくありませんね…。