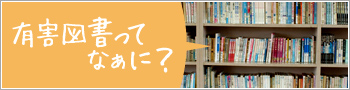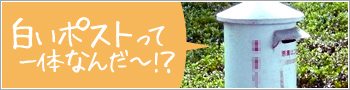ネット上から青少年に有害とされる情報を全て消そうという法律です
「青少年インターネット規制法」「青少年ネット規制法案」 とは、内閣府に設置される、最大5人までの委員による 「青少年健全育成推進委員会」 が、「青少年に有害だ」 と判断したあらゆる ネット の上の コンテンツ (マンガ や イラスト、写真などの 画像 や 動画、ブログ などの文章やテキスト、さらには SNS や 掲示板 や出会い系などの伝言・コミュニティサービス類の全て) を、業者、個人問わず網羅的に規制するための法律、法案です。
これらに該当するコンテンツ類や 書き込み などは、ネット上から即座に削除するか、フィルタリング を行うソフト会社への有害サイト報告を自ら行い、ブロッキング された状態で公開するか、もしくは年齢確認の上で パスワード による ログイン 認証の会員制にするなどの厳しい閲覧制限を設けなければなりません。
違反した場合 (有害情報を アップロード して削除に応じないなど)、当該情報やデータをネット上にアップロードした業者や個人が個別に厳しく罰せられるのはもちろん、その業者や個人が利用したインターネットプロバイダ (インターネット 接続事業者(ISP) や レンタルサーバ、レンタルブログやレンタル掲示板、SNSサービス業者、インターネットカフェ事業者、さらにはそれらを利用してコミュニティなどを 運営 しているサイト管理者なども 「有害情報削除義務違反」 として一律に処罰されます。 処罰内容は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
なお 「青少年有害情報」 の定義として、次の6項が法案の段階で挙げられています。
青少年インターネット規制法における 「青少年有害情報」 の定義
■ 第2条の2(青少年有害情報の定義)
この法律において 「青少年有害情報」 とは、次のいずれかの情報であって、青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。
| 1 | 青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの |
| 2 | 青少年に対し著しく残虐性を助長するもの |
| 3 | 青少年に対し著しく犯罪、自殺又は売春等を誘発するもの |
| 4 | 青少年に対し著しく自らの心身の健康を害する行為を誘発するもの |
| 5 | 青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの |
| 6 | 青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの |
この種の規制の 「取り締まるべき有害情報の定義」 は、あやふやで恣意的に取り締まろうと思えば何とでもなるような文言ばかりが並びますが、この法案のそれも同じで、「著しい」 とはどの レベル なのか、性の価値観などは人によって様々ですが、それを国が悪影響とそうでないものとどういう基準で何を根拠に定めるのか、分からないことだらけです。
また 「有害情報」 の詳しい内容はつまびらかになっていませんが、有害の度合い、含まれる割合や内容についての取り決めなども一切ないため、例えば有害情報が一切含まれない内容で5年間毎日更新していたブログでも、1つだけ有害情報が含まれるとされる レス や コメント がついたら、そのコメントやレスを即座に削除しなければ、そのエントリー、ひいてはそのブログ全体が 「有害ブログ」 扱いとなる可能性を秘めています。
サイトやブログ 管理人 はもちろん、それらのサイトやブログを数万から数十万、大手ポータル系企業ならば数百万の単位で扱う通信事業者が個別に監視活動を行うことは物理的にほぼ無理とされていて、事実上ネットでの自由な意見や 作品 の発表の制限、表現の自由 の著しい侵害、「検閲の禁止」 に反する行為に当たるのではないかとの危惧が ネット住民 だけでなく、大手インターネット企業などからも反対意見として上がっています。
ネット関連企業、利用者だけでなく、PTA会長や保護者からも批判続出
2008年4月23日には、ヤフー、楽天、マイクロソフト、ディー・エヌ・エー、ネットスターの5社が共同で 「ネット関連産業の発展を阻害する」 として反対を表明。 さらに同席した 「全国高等学校PTA連合会」 の高橋正夫会長は、「子供が情報の健全性を理解、判断し、活用する力を養えるような施策」 こそが必要で (ネットリテラシーの育成)、「子供や保護者の声を聞かず」 に決めた18歳以下の携帯電話利用者に対するフィルタリング規制の 義務化 なども強く批判しました。
自主規制では不十分、法律で国が規制すべき問題だと自民党 高市早苗議員
この種の 有害図書 や 「有害情報」 などの未成年対応は、青少年健全育成条例 などの有害図書規定により、出版社などの 自主規制 や、ゾーニング で長く対応してきた問題でした。 また性器の直接描写や特定個人の誹謗中傷などは、それぞれ 「わいせつ物頒布罪」(刑法175条) や 「名誉毀損罪」(刑法230条) などで既に違法化されており、二重に違法化する意味がありません。
ネット上でもフィルタリングソフトによる未成年者のアクセス制限など、これまでと同じ対応を業界は推進して来ました。 これに対して規制推進派は、「民間の健全化への取り組みは遅すぎる」「ここで動かねば政治の不作為と言われかねない」 として、自民党 高市早苗衆議院議員 (奈良2区) らが中心となって、2008年に急速に法制化に動いているという経緯があります。
その主な考え方は、これまでの 「未成年者にフィルターをかける」 やり方ではなく、「まず全てのネット利用者にフィルターをかけ、大人は自分でそれを解除する」 という取り組み方法の完全な逆転があります。 ただしこれは日本の国内法なので、例えば海外の サーバ から発信する情報にはなんら制限がかけられませんし、また罰則を設けるのも不可能です。 多くの違法アダルト業者は、そもそもが国内でサーバなどの稼動を行っておらず、「肝心の有害情報はほとんど取り締まれず、単に国内のネット文化を破壊するだけだ」 との意見にも、うなづけるものがあります。
なお野党である民主党も、高井美穂衆議院議員 (比例四国ブロック (徳島2区) が中心となり、ほとんど同じ法律案を2008年1月の段階で発表しています。 また以前問題となった、「青少年有害 環境 対策基本法案」(青環対法案、いわゆる 青環法) とも非常に趣旨や乱暴な規制方法が似た法律となっています。
自民党と民主党、形は違えど、ほぼ同じ内容の規制を検討
それにしても政治家や総務省の役人は、何でこうも揃って 「ネット」 を狙い撃ちにするのでしょうか。 例えば有害情報は何もネットや掲示板の中だけの話ではなく、公衆トイレや公衆電話ボックス、街の電柱なんかにもあふれています。 今回の法律では、公衆トイレの管理人や公衆電話ボックスの管理者、電柱の管理者に罰則付きで 「ピンクチラシやステ看板を監視し見つけ次第撤去しろ」「しなければ逮捕」 といってるようなものです。 近所に小中学校のある国道の電柱にホテトルのステ看板がくくり付けられていたとして、国土交通省の役人が撤去違反で逮捕なんかされるんでしょうか?
 しかもステ看板などと違い、ネット上の情報は、それが有害なのかそうでないのか、判断が非常に難しいものがたくさんあります。 それらをたった5人程度の委員による 「青少年健全育成推進委員会」 が定め、規制して良いのでしょうか? そもそもその 「青少年健全育成推進委員会」 の委員は誰が選び、どういう適性が求められ、またその判断の正しさの根拠はどこにあるのでしょうか? 得られる法益は何なのでしょうか?
しかもステ看板などと違い、ネット上の情報は、それが有害なのかそうでないのか、判断が非常に難しいものがたくさんあります。 それらをたった5人程度の委員による 「青少年健全育成推進委員会」 が定め、規制して良いのでしょうか? そもそもその 「青少年健全育成推進委員会」 の委員は誰が選び、どういう適性が求められ、またその判断の正しさの根拠はどこにあるのでしょうか? 得られる法益は何なのでしょうか?
中にはそういう法律があると、「撤去する大義名分ができた」 と思う管理者もいるかも知れませんが、ネットの場合はサーバスペースは利用者が利用規約を守るなり料金を支払うなりして借りているものですし、現時点でも利用規約に反するコンテンツのアップをしていたら、ちゃんと削除はできる訳です。
どうしてネットばかり2重3重に厳罰を課してまで規制したがるのか、単に 18歳未満の若年層保護の目的ではなく、何か別の理由があるのではと邪推もしてみたくなります。 ちなみにアメリカでは10年以上前に年齢制限義務化の法律は違憲判断が下され却下されてます。 その違憲理由をちゃんと調べてみたらどうなんでしょうか。
昨今、自民党や公明党、野党の民主党からも、「青少年を守るため」 と称して次から次へと罰則つきの厳しい言論規制の法律や法案が相次いで出されています。 しかもそれらの大きな反対運動を封じるためか、テレビや新聞、雑誌などの 「うるさ型」 マスメディアの規制は一切口にせず、ネットや個人発信の情報統制・言論規制にばかり邁進しています。
国民は、注意深く監視する必要があるでしょう。
関連する同人用語・オタ用語・ネット用語をチェック
○ 雑誌や出版物等に関する青少年関連施策